- 06
- 8月
あの日、母はまだ10歳の少女だった。その日も朝、学徒動員で,夏休みだが学校で勤労奉仕があり、学校に行く準備をしていた。玄関のあがりかまちあたりにいたときに
突然爆風にとばされ、気がついたときは瓦礫の下だったそうだ。どのくらい時間がたったかわからない頃、助け出されたそうです。
そのあと、少しはなれたところにいた母親と3歳の弟がみつかったが母親はケガをしていて逃げられそうにないので父親が母親を連れて逃げ、母は弟を連れて比治山に逃げるようにと言われたそうです。まだ10歳の母が3歳の弟をオンブして比治山に逃げるのは大変なことだったそうです。オンブして歩いているうちに黒い雨が降ってきて弟はぐずるし、そのうちやけどして逃げ惑う人達や川の中は死体だらけ、その死体の山を下に見ながら・・・・悲しみも、恐怖もそういう感情をしまったまま、何が起こっているのか?わからない状態で、とにかく山をめざしてすすんだそうです。
山についたときは夜で、朝までここにいて、朝になったら迎えに来ると言った父親の言葉を信じて、弟を抱きながら過ごしたそうです。この夜の山がほんとうに生き地獄で、うめき声、やけどしてただれた皮膚をぶらさげて歩き回る人、死体の匂い・・・・そのすべてが暗くなると未だに思い出され、大人になっても夜、電気を消して眠れないのはそのせいだと、母はよく言っていました。
幸いにも母の両親、弟は助かりました。助かったあとは、生き残った親戚もふくめ、バラック小屋に8人の同居生活。そこでは助かった母のいとこ(母よりも年の大きい男性)が、全身やけどで、その傷口からウジがわき、それを箸でとるのが母の仕事だったそうです。結局その方は亡くなり、母たち家族も再起をかけて、母の父親の弟(母のおじさん)を頼って倉敷に行ったのが、9月のお彼岸のころだったそうです。
ところが、その倉敷での生活も大変でした。、頼ったおじさんの家族は乳飲み子も含め8人の子だくさん。肉屋をしていましたが狭い家に居候するのは大変な状況で、遠慮して生活しているうちに、母の母親は精神を病み首吊り自殺をしてしまいました。それを発見したのがまだ10歳の母。(時々、夏など着たあとの浴衣をハンガーにかけて部屋にかけていると、母が尋常じゃなくびっくりしていたのはこのときのことを思い出すからだとあとから聞きました)
そしてその1年後気丈に頑張っていた父親も原爆症でなくし、それからは3歳の弟と2人で懸命に生きてきたそうです。
・・・・母はその時のことを「本当は大阪で生まれ、鍼灸師をしていた父と母と弟と貧しいながらも楽しい家族だった。1945年の6月の大阪空襲で住まいを焼かれ、本家のあるご先祖様のいる広島ならまもってくれるだろうと、一家で広島にいったのに、それから一ヶ月で被爆するとは・・・あのまま大阪にいれば・・・神もご先祖様も関係なかった・・・・
親がいないことや被爆者だからと差別をされるのが嫌で、なんでもがんばった。どんな苦労もあの被爆体験よりましだと、頑張ったんよ。学校の成績もよかったけど、子だくさんのおじさんたち夫婦に育ててもらっただけでもありがたく、学校に行きたいとも言えなかった、夢も将来も、家族も何もかも奪うのが戦争じゃ、もう2度とこんな想いを、子、孫にさせてはいけん」と、よく言っていました。
それでも母が被爆体験を話すようになったのは、50歳を過ぎていました。話すことも勇気がいったのだと思います。そんな被爆者達の思いをたくさん背負って私たち2世も次の世代にしっかりとつたえていけないといけません。二度とこんな思いをだれにもさせないために!!


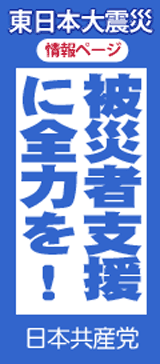



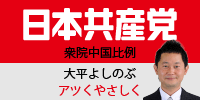

09年8月7日 7:48:12
そうでしたか。まさか比治山の地名が具体的に出てくるとは思いませんでした。
先日、野球解説者の張本さんが被爆体験のことを全国紙に投稿されていました。
同じ時刻に多くの人々がこの世ではあり得ない阿鼻叫喚の巷と化した世界にさらされ想像することさえ恐ろしくもあります。
張本さんは2年前にやっと原爆資料館に入ることができたそうです。背中を押したものは、小さい子が原爆が何処に落とされたかさえ知らない現実だと記されていました。
映画監督の新藤兼人さんが2年前の8月15日の徹子の部屋で原爆の落ちた数秒間、瞬間を撮りたいとおっしゃっていました。原爆はこんなにひどいものだと全世界の隅々まで知らせたいと・・・・。しかし娯楽映画ではないので莫大な費用が掛かることを悩んでおられました。その後どうなったかは知りません。
赤裸々な書き込みを読みましてこころが揺さぶられました。
09年8月7日 11:12:59
憲法9条が光りますね。
核兵器の廃絶を。
09年8月8日 8:34:38
サンデイーさん、ありがとうございます。本当に体験している方の傷はなかなか深いと思います。「聞いた話」だから私たち2世は、簡単に話ができるのかもしれません。
それでも伝えていくことが大切だと思います。
実はこの話、朗読劇にしていて、過去3回披露したことがあるんです。
また、いつか、指笛とコラボして、朗読劇ができたらいいなーとおもいます。
その時はご協力を!!
大野さん、
ご一緒にがんばりましょう