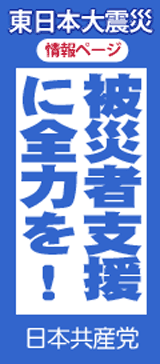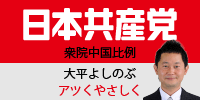タイムリーな報告はほとんど、フェイスブックとインスタグラムの方でおこなうこととなり、なかなかブログを書けず・・・・
それはパソコンに座る時間がなかなか取れず、待ち時間や、お布団の中でも気軽に更新できるスマホでできるほうが優先となってしまうからです。
なのでブログはタイムリーな報告でなく、エッセイ的な内容を記録する為に書く事とします。
さて私たち党市議団では議会ごとに、市政報告会を5人揃って行っています。
これは今のメンバーになって始めたことで、できるだけ議会ごと、全ての区で開催しています。
今回は日程が取れず、一箇所だけ南区だけの報告会となってしまいました。
この日は土曜日ということもあり、子育て真っ最中の東議員と田中議員は子連れ参加となりました。参加者が子守をかってでてくれアットホームな報告会となりました。
赤ちゃんがいるとそれだけで和み、未来を感じます。
しかし保育園には入れないことは深刻、毎日のように私にも、保育園には入れないという相談が入ってきます。岡山市だけでなく、最近は赤磐市など近隣の市の相談も入るようになりました。なんとしても認可保育園を増やしていかなければいけません!!
この日の報告も保育のことは会場からも話が出て、公立幼稚園保育園の30園の認定こども園として、他は統合民営化という市の方針を、撤回してもらう運動をと意思統一されました。
後楽館高校跡地の売却問題や介護保険の問題など会場の皆さんとしっかり語り合うことができました。
政務活動費の使い方の問題も議論になり、私たちは領収書を以前から公開しておりオンブズマンの裁判でも返済指摘はないことなどを報告。
きっちりと調査活動を行うための事務局職員の養成などには使いたいという私たちの考えも説明しました。
11月4日に東区の連合町内会長と東区選出の市会議員との懇談会がありました。
東区計画について、区別の特別委員会をつくり話し合いをしているのでその報告とく計画に盛り込んでほしいことを町内会長さんたちから伺うという目的です。
やはり、道路のこととか企業誘致、雇用などの要望が多く・・・
ここでは聞くことがメインなので議員同士の政策論争はやるべきではないとできるだけ超党派で一致していることを申し上げ意見を聞き置くという立場で参加した。
それはほかの議員も暗黙の了解のような感じだと思っていたが、ある方だけは独自の政策を何度も繰り返していた。その内容が東区をCCRC構想の地域にとの提案。
元気なうちに高齢者が移り住んでひとつのコミュニテイを作りそこで健康寿命を延ばしながら高齢者同士支え合いながら看取りまでという考え。
今国がまちひとしごとの構想の中で急に提唱しだした考えです。
その中で療養病棟のベット数が削減することなども言われていたがそもそも自民党が医療報酬の削減、療養病棟のベッド数の削減、そして平成の大合併で、地域を住みにくくさせておいて、今更高齢者は固まって住んで助け合って・・・なんて!!!と
論争したかったけどそこはそういう場ではないので避けましたが・・・
生まれ育ったまちで老いても安心してできれば自分のおうちで家族に看取られたい!というささやかな願いが叶うような街にどうすればできるのかが私は大事だと思います。
そして施設に入らざるを得ない方も、施設でも家と同じような人間らしい暮らしを提供し看取りまでというならもう東区でも実践されている施設もあるので、出来ると思うのだけどなあ~~~
話がそれましたが、町内会長さんたちからは最終的には学区弾力化の問題や、保育園の問題まで出てしっかりと意見も聞け有意義な時間でした。
介護保険推進サミットin岡山が、20,21日と岡山シンフォニーホールを中心に開催され、参加しました。介護保険が出来た頃から全国で開催されているもので、介護保険推進の立場のサミットです。しかし、今日のシンポジストの稲城市の副市長さんの言われるように、介護保険は、どういう地域づくりをするのか?の道具の1つであり、いいところは使い、足らない部分は行政がつくればよい!という姿勢は大変参考になりました。また私が個人的に楽しみだったのは、豊中市のカリスマ?コミュニティソーシャルワーカーの方のお話。例のNHKドラマで深田恭子さんが演じたモデルになった方。地域に入り込んで問題をみつけみんなのものにして地域で解決でき、支え合うシステムを作るとの働きぶりに、どこの社会福祉協議会もそうなればとの感想が司会の方から漏れました。
全く同感。
2日目は実り多い内容でした。
特に基調講演の世田谷区立特養ホームの石飛幸三医師のお話。済生会病院の外科医として、胃瘻や気管切開など穴をあけることで延命をしてきたけど、これでいいのか?と思い、特養に変わった時に間違いと気づいたこと。人生の終末期に自然にその人らしく最期まで生きていただくのに、胃瘻などの延命措置は間違い、平穏死が自然の姿だと気づき実践している報告でした。ホームで看取るということはどういうことか?
もう病院がお手上げ、食べないと死ぬから胃瘻をと勧めた患者をホームに連れて帰り、本人の好物を食べたい時に食べていただく。あくまでも周りは伴奏者でいいのだと。
私も現場にいて、胃瘻や気管切開に疑問を感じ、議員になってからもそういう相談があった場合、本人は苦しいばかりだから、個人的には勧めないけど、医者がいうのなら、家族が納得するまで話し合ってくださいと、返事していた。
今日の石飛先生のお話で、まちがってなかったと感動しました。そして人生の最期に寄り添う介護士は感情労働で良いのだ、介護に医療はできないが時にそれは医療を超えると。介護は自分を成長させると言い切ってくださることに、またまた感動。
いいお話でした。
あらためて介護の仕事は人権擁護の集大成であり、素晴らしい専門職だと思いました。だからこそもう少しそれに見合う専門性と報酬が必要ですね。
あとは介護保険を作った立場の厚労省の方の報告があったり、地域での包括ケアの実践者の報告があったりと盛りだくさんの内容でした。

「こんにちは日本共産党の竹永みつえです」ニュース No.66を掲載します。
多様性のある社会実現特別委員会がありました。
この期初めて出来た委員会で自民党の男性議員さんからの提案で実現となった委員会です。時代は大きく変わったと実感します。
もう十年以上も前に、性的マイノリティの問題を議会で取り上げた時は当局も議場も反応あまりなく・・・それでも女性議員は超党派で上川あやさんという東京世田谷区の性同一性障害の区議会議員のお話を聞く会をしたりなど継続的に勉強していました。そして世の中もこの問題を自然に取り上げることが多くなり、議会も自民党の男性議員が複数とりあげ、LGBTという言葉も初めて使い議場で質問されました。
まさに機運がたかまり、この特別委員会の設置となりました。委員長をさせていただき、視察先も昨年は民間会社に行ったり工夫をしました。そして今年の視察は、来月沖縄那覇市に行くことになりました。
那覇市は性の多様性を認め合う宣言都市であり、同性婚を事実上認めるパートナーシップ制度も導入しており先進都市です。
そしてこの問題を6年間も取材してドキュメンタリー番組を作成したテレビ会社のデレクターとも会えることになりました。とてもみのり多い視察になりそうで今から楽しみ!
そのためにもこの委員会で予習も兼ねて、そのテレビ番組「にじいろ~性同一性障害・多様な明日へ~」を視聴しました。
10人十色の多様な性があること。どんな夫婦の形もありで、同性や性転換をしても当事者が生殖補助医療などで子どもを望み育てることが
できることなど未来につながるお話でした。
また、今回、プラウド岡山という団体が市民共同事業でLGBT啓発のパンフレットを作成し各課で生かすことや、これをもとに教育委員会は教職員研修のマニュアルを作成するなどが報告されました。
担当職員も那覇市のDVDを見て、ここまですすんでいるとは・・・と岡山の現状との差を実感されていました。
これからです・・・・特別委員会としてもできることを頑張ります






10月のさいさい子ども食堂が8日に開催され35人のこどもたちが食べに来てくれました。この日はハロウィンDAYと広報すると、アリスやお姫様、かわいい悪魔さんなどコスプレで来てくれる子どもたちもいました。
そしてメニューもハロウインカレー.
かぼちゃを入れて炊くと黄色いご飯ができ、人参の型どりや,
のりでコウモリなどをつくり、サポーターのおばちゃんたちが頑張りました。
こどもたちが笑顔で美味しいと言ってくれ、中には4杯も食べる子も!
この日は、城東台かるがも文庫さんもボランテイアに来てくれ、お手玉や、紙芝居、折り紙など子どもたちも大喜び。
宿題をちゃんとして遊ぶと自分で決めている子もいて、土曜日の過ごし方として定着しているのかな?居場所となっていけば幸いです。
また天気が良かったので外遊びもしたがり、スケーターなどを持参してくる子もいたので、お兄さんボランテイアに見守ってもらい、初めて
外遊びもできました。目一杯食べ、遊んでと帰るという過ごし方ができたようです。
近所の大人も食べに来てくれました。また、特別養護老人ホーム中野けんせいえんの地域センターをお借りしているので、面会に来た高齢者も食べて帰り、こどもたちと触れ合うシーンもあり微笑ましかったです。
中にはよく飛ぶ、紙飛行機の飛び方を伝授してもらっている若いママの姿もあり、自然に世代間交流ができていました。
今回も、じゃがいも、コーン、さつまいも、かぼちゃ、コメ、栗などたくさんの食材提供やカンパも寄せられ、みなさんの善意でなりたっていると感謝です。
こども食堂は、大人の都合で始まり、大人の都合でやめてはいけない、継続することが一番の課題ということですから、持続していこうを合言葉にサポーター、一同決意を新たにしました。この日も20代のサポーターを含め3人新しいサポータが加わり、輪も広がってきています。