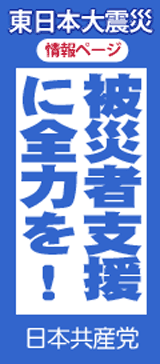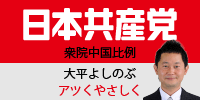- 19
- 8月
- 15
- 8月

お盆です。いつもは姑を連れて夫の里に帰り、泊まり込みで規制するのですが・・・今年は姑の認知症がすすみ、帰りたいとも言わずデイケアだけを楽しみにしているので、デイケアに行っている間に強行突破し日帰りでお墓参りだけを済ませました。
夫の里は、真庭市美甘です。県北の2000人ほどの小さな村でしたが合併され真庭市となりました。
とにかく緑と空気がきれいでかえってこの景色を見るだけで癒されます。
私は商店街で育った街の子だったのではじめはこの田舎がいやでいやで・・・・
なんにもない、時間がたつのが遅い、人間関係が濃い!
そのすべてが今は楽しめます、何にもないところでボーっとすることのうれしさ、時間がゆっくり流れることの喜び、そして濃い人間関係をこちらからどっぷりつかってしゃべりこむのも好きになりました。不思議ですね・・・・
子どもたちが小さいときはまだ姑も美甘に暮らしていたので長い夏休みの一週間くらい預かってもらっていました。その頃は、コンビニもない!虫が多い、遊び道具がない!などなど文句ばかり言っていた子どもたちも、今は田舎にふとした時に帰りたくなるようです。
田舎、ふるさとのあるありがたさを感じています。
- 10
- 8月
- 10
- 8月

今年も夏祭りの季節です。東区は学区でのお祭りが多く、町内だけのお祭りは地元では数か所となりました。6日の土曜日もあちこちの学区で行われており、回らせていただきました。豊学区では母校の、旭川荘厚生専門学院の学生さんが頑張っています。私もこのころ18歳から20歳まで、朝6時から9時まで旭川荘の児童院でアルバイトし、そのあと学校に行く日か、学校に行ったあと夕方から夜九時まで児童院でバイトという交互の日程で、あいている夜は飲食店でアルバイト、土日はボランティアというハードな日々でした。青春だったなーと皆さんの笑顔にキュン!となりパチリ。
そしてある学区ではその旭川荘時代に一緒に頑張っていた支援学校の先生たちがバンドを組んでいて懐かしい歌が聞こえびっくり~という出会いもありました。
そしてどこに行っても、あちこちで地域のために汗を流し、損得なしに頑張っている皆さんに励まされたのでした。
- 08
- 8月

被爆2世・3世の会の初の全国交流会が8月5日広島でありました。
岡山は昨年2世・3世の会ができたばかり、岡山から6人の参加。岡山から参加した二十歳の学生が、アンテナを高くしてつながっていきたいという未来につながる活動のあり方を提起し励まされました。
被爆者の健康調査をしていろ広島共同病院の青木ドクターの話を伺い、あらためて2世・3世も被害者なんだと実感。2世・3世の健康調査アンケートでは、小さい頃から鼻血をよく出す、貧血、アトピー、ぜんそくなどの症状がある方が多いとの結果、私も原因不明の万年貧血、これは若いときから、うちの子どもたちも鼻血をよく出していたし、次男はアトピーでした等々考えるとやはり因果関係をはっきりしてほしいと思います。国は内の一点張り。まずは2世・3世で実態調査をする必要があります。大きな宿題をいただいたのと、被爆者自身の高齢化の中できっちりとそのことをつなげて提起できるのは2世・3世だけです。がんばらなくては!
日本共産党の笠井あきら衆議院議員も2世と言うことで参加されていました。国に2世の健康調査の予算化もふくめ、責任をとらす運動をと力強く訴えられました
- 04
- 8月
出来たばかりの、瀬戸内市立図書館・もみわ広場を鬼木のぞみ議員たちと訪問。



 もちより
もちより
みつけ
わけあう という理念のもともみわ広場と名付けられた市民の市民による市民のための図書館というコンセプトがすみずみまで生きている図書館だと感じました。お話をしてくれた島田館長さんは、図書館愛の溢れる方で、私たちに説明してくれながらも、椅子の並びを直したり、館のすみずみまで目配り気配りしておられました。よりよく館を使ってもらおうという気持ちがこちらにも伝わってきました。デザイン的にもとても素敵で、木づくりと空間がほど良く、居心地のいい図書館でした。
一緒に行った方が、呼吸する図書館と感想を言われてましたが、本当にそんな感じ。
空間の取り方もよく、カウンター席の一列の利用者の姿は圧巻でした。
利用者の立場を理解して作られているからでしょう。
移動図書館も、この素敵な花柄の車で、高齢者施設などに回っているとか。
例えば回想法を実践する施設があるとそういう本を揃えて持って行くなど、ニーズにあった提供をしているそうです。
ただ、こんなにもがんばっているところが、もみわ広場と、長船、牛窓の三館合わせて5人の正職と5人の非正規の10人という体制だそうで。もう少しなんとかならぬか?と思いました。
子どものコーナーには隠れ場所的な読める部屋があったり、子ども用の小さなトイレや授乳室もありどの世代にも対応できるようにしてありました。
本棚の上にある説明文も、「子どもに寄り添う」「大人になって学ぼう」などニーズにあった説明文があり、ここも利用者目線が感じられ感動しました。
そして、文化の地産地消というコンセプトのもと、歴史的な土器や人形などの地域の歴史や文化とコラボしてる展示や場所が確保されていました。
その根底に、長い間、あきらめず市民のための図書館を!と運動して来られた市民の皆さんのアクションが続いていたからだということもよくわかりました。
12回にもわたる市民のミーティングでコンセプトや設計も変わったとの事。
これからも市民とともに成長する図書館になると思いました。
岡山市も図書館行政先進都市と言われており、長い市民運動が根底にあります、今日の学びを岡山市にも活かしていきたいと思いました。